
昆布は生育する場所により、品質、風味などの商品上の価値に大きな違いが現れるため、種類・性状・用途などによりたくさんの銘柄と等級に分けられています。
5月1日から通常の採取期日(7月10日~7月20日ごろ)までに採取される2年生のもの。
解禁日(だいたい7月10日~7月20日ごろ)から9月10日前後までに採取したもの。
![夏採(なつどり)[走(はしり)]](assets/images/page7/ico_collection01.webp)
9月10日前後より終漁期までに採取したもの。
![秋採(あきどり)[后(ご)]](assets/images/page7/ico_collection02.webp)
時化など何かの理由で漂着した昆布で成昆布のもの。

1年生(若生い)昆布のもの。

前年度に生産されたもの。

上記のほか、干場を区分した砂付き・無砂・草干、また天然・養殖などの分類があります。
長さ、葉重量、葉幅、結束などにより規格化され等級が定められます。
以前は長いまま根元をそろえ、その何箇所かを昆布で作った縄でしばって製品としていました。現在は、根元をそろえるのは同じですが、羅臼昆布はほとんどが75cm、真昆布は90cmの長さに折って結束します。
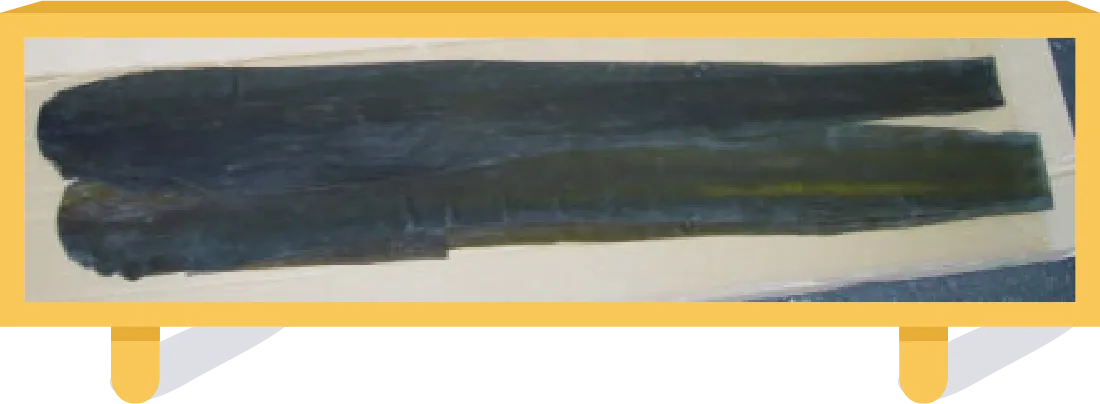
昆布を75cmから105cmの一定の長さに切りそろえて結束したものです。

20cm~60cmの短い長さに切り結束したものです。
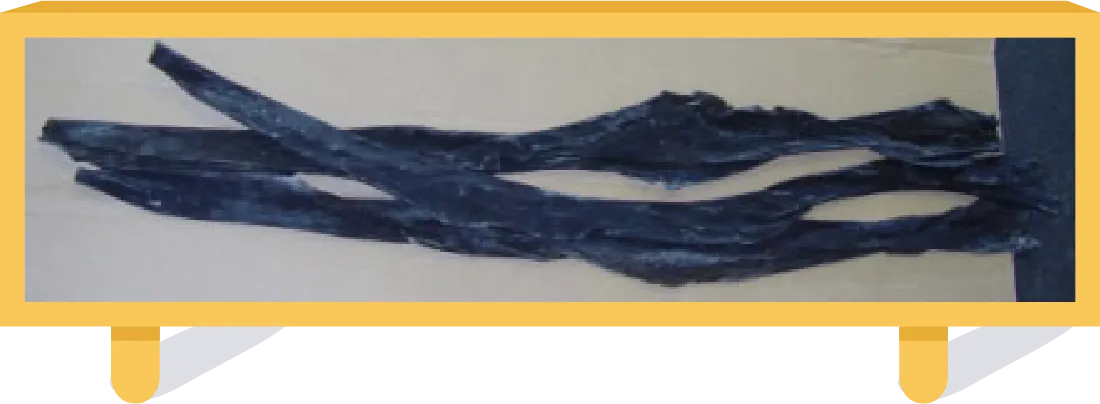
切らずに27cm~75cmの一定の長さに折りたたんで結束したものです。
切り落とし部分、色の悪いものなどで上記の4種類の規格にあわないものを俵詰めにしたものです。

真昆布、利尻昆布、羅臼昆布、日高(三石)昆布、長昆布など。
天然、養殖(促成)の順の格付けとなります。
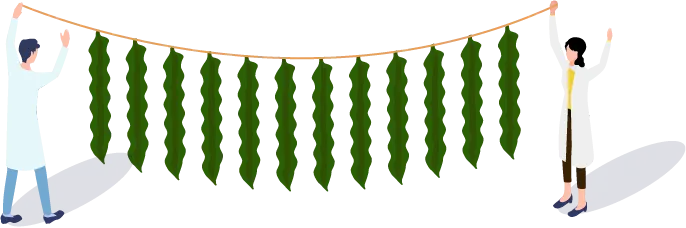
昆布は発育する場所(浜)により、品質や正常などに微妙な差が生じます。その年により多少の変動がありますが、浜別の価格構成を行います。
同じ浜の昆布であっても、葉のかたちや選別、光沢などから1等~6等までの格付けが行われます。 この検査の規格は昆布のいろいろな区分や形態により決められています。
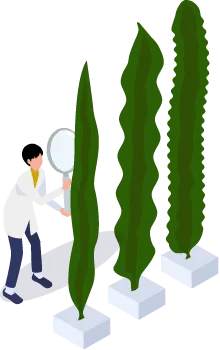
発育場所の深さ(深度)などにより「沖」と「岸」にわかれ、一般には「岸」の方が格上です。