
Q:昆布にまれについている透明な粒は何ですか?

A:昆布の成分が固まったものです
透明な粒は、アルギン酸をはじめとした水溶性食物繊維などの昆布の成分が固まったものです。 昆布の表面に浮き出た水溶性食物繊維などが、昆布を乾燥させた際に、固まって透明な粒になることがあります。 元々昆布に含まれていた成分であり、品質に影響ありませんので、安心してお使いください。

Q:昆布にまれについている白い粉はなんですか?

A:うま味成分が表面に現れたものです
白い粉の正体は、昆布から出てきたうま味成分で、マンニットと呼ばれるものです。 昆布にもともと含まれる成分であり、品質には影響ありません。 そのため、洗い落とさずに、固く絞ったぬれ布巾でさっと表面を拭く程度で、お使いください。

Q:昆布でだしをとろうとしたら、青っぽくなりました。
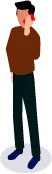
A:ヨウ素デンプン反応によるものです
ヨウ素でんぷん反応によって、青~青紫色になることがあります。 昆布にはヨウ素が含まれています。手や鍋・器に、でんぷん質の食品(お米やうどん、じゃがいも、さつまいもなど)がついていて、塩素を多く含む水道水に昆布を浸した場合、ヨウ素でんぷん反応が起こり、青~青紫色になることがあります。 品質に影響ありませんので、安心してお召し上がりください。 また、加熱することにより、その色は消失します。
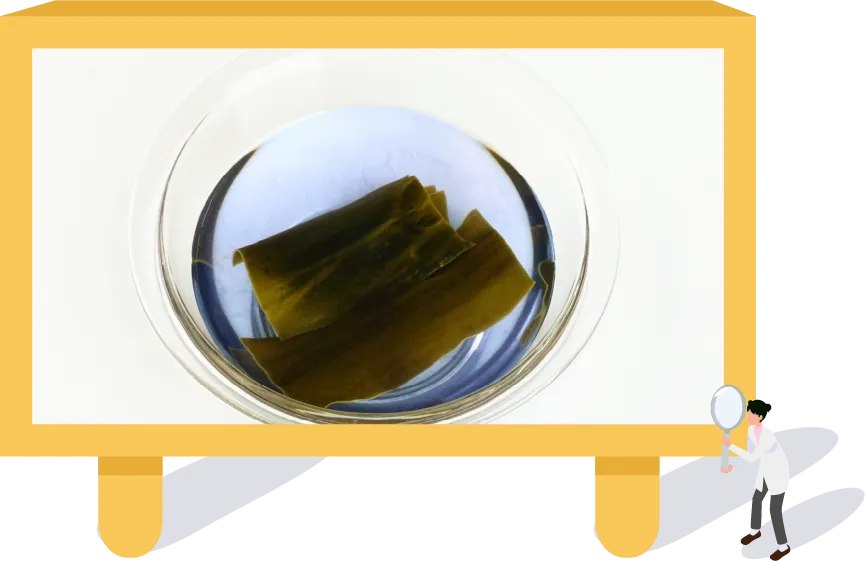
Q:昆布でだしを取ったら、だし汁が茶色になりました。

A:昆布の色素の一つであるカロテンの色です
昆布には、ニンジンにも多く含まれることで有名なカロテンが含まれており、昆布の生育した環境や時期によっては、これが多く含まれるものもあります。品質には影響ありませんので、安心してお召し上がりください。
Q:昆布でだしを取ったら、だし汁が緑色になりました。

A:葉緑素によるものです
昆布には葉緑素が含まれており、それがだしに流れでたものです。品質には影響ありませんので、安心してお召し上がりください。
Q:昆布がヌルヌルするのはなぜですか?

A:アルギン酸・フコイダンによるものです
アルギン酸やフコイダンという成分は、水に濡れるとヌルヌルとする性質があり、昆布はこれらが多く含まれているため、ヌルヌルとします。 ちなみに、大阪城の石垣を作る際、濡らした昆布で摩擦を軽減して巨石を運搬した、という説もあります。
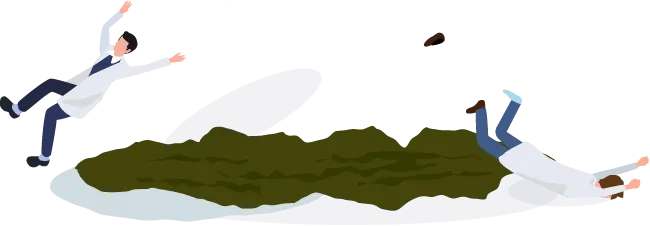
Q:昆布は日本でしか食べられないのですか?

A:いろいろな国で食べられています
昆布は日本特有のものと思われがちですが、各国でも食べられています。例えば中国、韓国、ロシア、ウクライナ、アメリカなどでも食べられています。
炒め物やスープなどの具として食べられています。

昆布の缶詰や刻み昆布が主で、野菜の代わりのような形で食べられています。
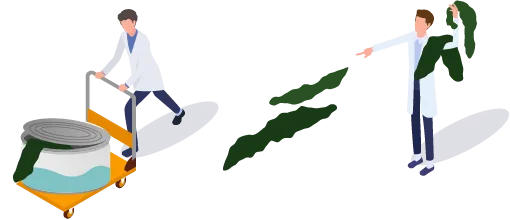
近年の日本食ブームで多く食べられるようになってきました。
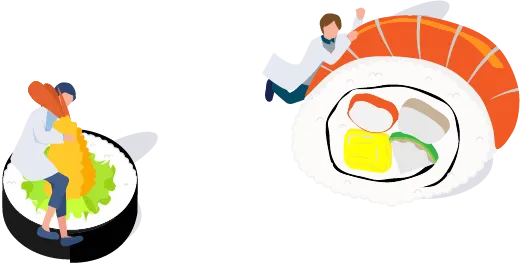
ちなみに、「kombucha」という飲料がよく飲まれていますが、これは日本でも流行った「紅茶キノコ」のことで、昆布とは関係ありません。

フランスではまだ食文化として定着しているとは言いがたいですが、フランス料理に昆布だしを使用する例が現れています。ミシュランに掲載されたあるレストランでは、昆布だしを常にストックしているという話もあります。

Q:昆布は養殖もされているのですか?

A:養殖も行われています
収穫される昆布のうち、約30%が養殖された昆布です。
Q:昆布はどれくらいの量が採れているのですか?
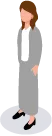
A:年間13,000トン程度です
日本では、年間13,000トン前後で推移していますが、地球温暖化や昆布漁師の高齢化などの影響から、漁獲高が減少し続けています。
Q:おいしい昆布はどうやって見分けるのですか?

A:緑がかった褐色のものです
上質の昆布は緑がかった褐色でよく乾燥し、香りがよく、肉厚のあるものです。逆に黄色がかったものは味が落ちます。また、時期はずれに採取されたものは、色が黒々しており、だしも十分にとれません。

Q:だしがら昆布はもう使えないのですか?

Q:海の中でだしが出てしまわないのはなぜですか?

A:「選択透過性」という機能があるからです
昆布を形作る細胞を包む細胞膜には、昆布が生きていくために必要なものを吸収し、不要なものを排出するという「選択透過性」という機能が備わっています。これは昆布に限らず、細胞を有するあらゆる生物の持つ基本的機能です。
だしの元である「グルタミン酸」は、昆布が生きていくために必要な成分なので、昆布が生きている間は「選択透過性」が働き、だしが出てしまうこともありません。
Q:なぜ「昆布」という名前がついたのですか?

A:由来は諸説あります
もともと、日本では昆布のことを「ひろめ(広布)」や「えびすめ(夷布)」と読んでいました。昆布の語源に関しては、「ひろめ(広布)」を音読みにした「コウブ」がなまったとする説、アイヌ語の「コンプ(=昆布)」由来とする説、中国語「綸布(カンプ)」由来とする説があり、はっきりとしていません。
「昆布」という記述が日本語の書籍に現れたのは、797年に成立した「続日本紀」です。
Q:昆布を食べると髪の毛が生えるのですか?

A:科学的な根拠はありません
昆布を食べると髪の毛が生える、黒くなると言われていますが、実は科学的な根拠はないと言われています。髪の毛の主成分はタンパク質ですが、これは昆布にはほとんど含まれていません。
しかしながら、昆布にはヨード(ヨウ素)と呼ばれる栄養素が豊富に含まれています。これは、新陳代謝を活発にして、成長ホルモンの分泌を活発にすると言われていますので、髪の毛のつやをよくしたりする効果はあるかもしれません。

Q:おせち料理に昆布が入っているのはなぜ?

A:「よろこぶ」とかけた縁起物だからです
昆布は昔から縁起物として親しまれてきました。戦国時代には、出陣前に、打鮑(うちあわび:あわびを薄長く切って伸ばし、干したもの)、勝栗(かちぐり:干した栗を臼でつき、殻と渋皮を取ったもの。臼でつくことを「かつ」とも言うことから)と昆布を食べることで、「打ち勝ち喜ぶ」という語呂合わせで戦勝祈願をしていました。この時期から、「昆布」と「喜ぶ(よろ『こんぶ』)」をかけていたのです。
昔から、昆布は「よろこぶ」に通じる縁起物として親しまれていたのですね。
また、同様の理由で鏡餅を飾る際にも昆布を使用します。昆布はお正月には欠かせない食材なのです。

ちなみに、昆布が縁起物として利用されているのはおせち料理だけではありません。
相撲では、場所が始まる前に土俵祭という行事が行われます。その行事では、場所の成功や安全を祈願して、縁起物として勝栗や米、スルメ、塩、かやの実とともに、昆布が土俵の中心に埋められます。
また、結納においては、「こんぶ」を「子生婦」と書き、子孫繁栄を願う品物として使用されます。 (婿養子の場合は「子生夫」「幸運夫」と書く場合もあります)